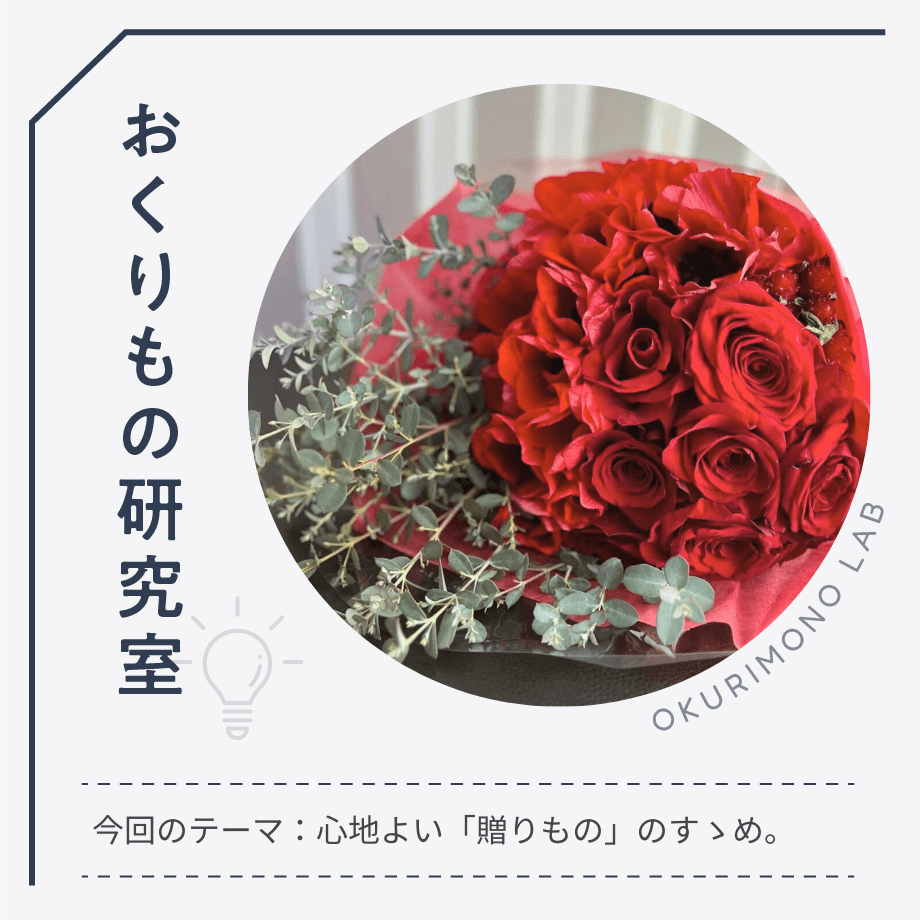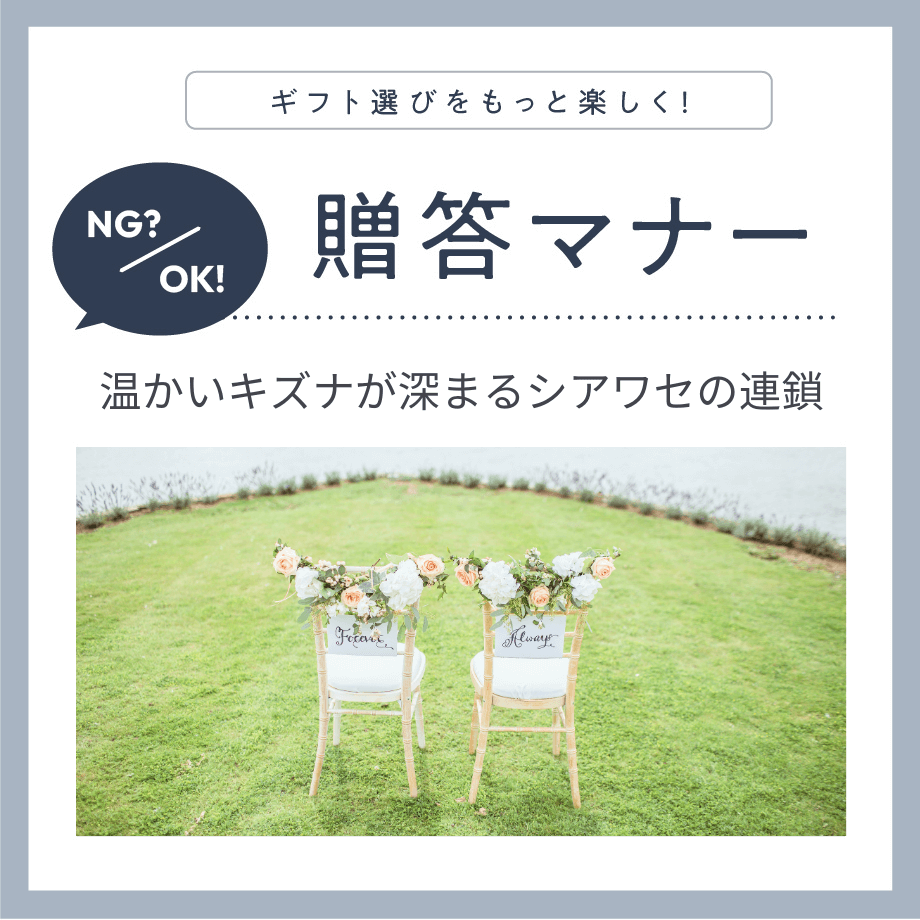最近では「ギフトコンシェルジュ」という言葉が定着しつつあり、それに伴ってギフト専門メディアにもさまざまな質問が寄せられています。ギフトコンシェルジュとはどんな職業なのか、なるにはどうすればいいのか、どういった資格や知識が必要なのか――。言葉の響きや定義に興味を持たれている方々も多くいらっしゃいます。
ギフトコンシェルジュとは広い意味で言うと、贈り物をする人に代わって贈り物をえらぶ専門家のことを指します。ただ、肩書きやサービスの名称、職業など、さまざまな解釈で捉えられることがあり、明確なことばの定義は存在しないとも感じます。発祥はアメリカだと言われていますがそれも定かではありません。
そこで今回は、日本においてギフトコンシェルジュの第一人者である「裏地桂子さん」にインタビュー取材を行ないました。裏地さんが考えるギフトコンシェルジュの在り方、必要な知識や心掛けなど、第一線で活躍されている専門家としての意見をうかがうとともに、ギフトコンシェルジュを志す人に向けたメッセージをいただきました。
この記事はこんな人におすすめ!
- ギフトコンシェルジュという肩書きや職業に興味をもっている人
- ギフトコンシェルジュを志していて第一人者の意見を聞いてみたい人

[ 取材対象者 ]裏地桂子さん
ギフトコンシュルジュ/文筆家/草月流師範
ハイエンドな女性誌のライターとして活躍後、雑誌や企画展などの商品セレクションをはじめ、ブランディング、ショップのプロデュースや商品企画、商品開発などを手がける。著者多数。毎日、更新のInstagramも人気。

[ インタビュアー ]河野ひろこ/ギフトコンシェルジュ
看護師時代に培ったホスピタリティを活かし「人となり」を想像したプレゼントの見立てが得意。二児の子育てに日々奮闘しながらも、ギフトセレクトとショップ・カフェ巡りがライフワーク。
INDEX
ギフトコンシェルジュとはどんな職業なのか?
そもそもギフトコンシェルジュとは、サービスの名称を指すのか、肩書きや⽴場のことなのか、職業のことなのか、明確な定義はあるのでしょうか? 結論としては、ギフトコンシェルジュという言葉の解釈は多様で、そのどれもが間違っていません。
抽象的に言えば、ギフトコンシェルジュとは贈り物をする人に代わって情報を収集・整理し、贈り物を選んでスタイリングすることや人を指します。つまり、ギフトに関するさまざまな悩みを解決するサービスや専門家のことです。

ギフトコンシェルジュの発祥はアメリカだと言われていて、セレブやVIPなどの顧客に対してハイグレードな贈り物を選んだり、コンサートの手配や旅行のプランニングなどを行なう相談役のようなサービスが欧米を中心に展開されています。
日本では職業として捉えられることは稀です。百貨店やデパートに設えた顧客サービスとして、冠婚葬祭に則ったギフト選び、熨斗やラッピングといった贈答マナーのケアに至るまでのサポートが一般に広く知られています。
また、裏地桂子さんや筆者である河野ひろこのように、肩書きとしてギフトコンシェルジュを号する専門家もいて、個人・法人に対するパーソナルギフトの提案、製品ブランドのプロモーション、商品企画や監修支援、メディア出演や媒体協力に携わったりします。

インタビュアー
裏地さんにとってギフトコンシェルジュとは何でしょうか?

裏地さん
やっぱり「お福分け」かなと思っています。相手の笑顔を見たくて”ハッピー”を共有するイメージです。
お福分けとはよそからもらったものを分けることで、お裾分けとほとんど同一の意味ですが、特におめでたい行事や慶事で相手が幸福になるよう願って贈るもの。日本では昔から、お正月や祭りなどおめでたい日に”ぜんざい”を食べる習慣があり、当時貴重だった小豆を振る舞うことでお福分けをしていたそうです。
裏地さんがギフトコンシェルジュを肩書きにした経緯

裏地さんは元々習いごとやウィンドウショッピングが好きで、その当時、雑誌購読は月50冊に上るほど没頭していたと言います。そして、30代で女性誌ライターとしての活動を本格的にはじめ、それまでの地盤を活かし “ホンモノを見極める目” を磨いていったそうです。
ライターを経て「クリエイティブコーディネーター」という肩書きをつけた頃に転機が訪れます。人物の仕事や生活ぶりに密着するドキュメンタリー番組から取材を受け企画を練るときに、過去にそう呼ばれることもあった「ギフトコンシェルジュ」が分かりやすく、肩書きとして据えることになりました。

インタビュアー
プロデュースもされていたので、”ギフト”という分野でも違和感がなかったのですね。

裏地さん
はい、元から「お福分け」がモットーで、喜んでいただけることが嬉しいと感じていましたので。周りの方々もピッタリだと言ってくれました。
裏地さんがギフトコンシェルジュを肩書きにしてから、テレビや雑誌でギフトをセレクションするお仕事の依頼も増えたと言います。そして次第にギフトを選ぶことだけでなく、企業やショップでアドバイザーを務めるなど、小さな波が大きな渦へと変わっていく力になったのです。
ギフトコンシェルジュになるにはどうすればいいのか?
まず「肩書きと職業は違います」と裏地さんは語りかけます。資格として存在する訳でもないため名乗ることで肩書きになり、誰でもギフトコンシェルジュになることができるのです。ギフトコンシェルジュになりたい人は「自分で言い切って、自分で発信する」ことが大切だと教えてくださいました。

裏地さん
そもそも日本人全員がギフトコンシェルジュなのではと思っています。ギフトをコンシェルジュするって素敵ですし、ハッピーにする言葉ですよね。
裏地さんが必要だと感じる素養・知識・経験など

裏地さんは、ギフトコンシェルジュとして信頼を得るために、贈り物に関してさまざまな知識を養うべきだと言います。日本に生きて日本人に贈る、そしてそれを提案する以上は、日本のしきたりや四季、贈答マナーなど、伝統的な文化を勉強することが大切になってくるのです。

裏地さん
私自身はお花とお茶を学んでいます。そういった伝統文化に触れることも大事かなと思います。
同じところに行き、同じものを見たとしても、贈りもの選びのセンスを磨くことは難しいことです。裏地さんの経験上、まず人ではなく「自分が欲しいもの、自分がいいと思うものを確立する」ことが必要だと感じているそうです。自分の好きなものを選べる=自分の基準をしっかり持っていることで、物選びが信頼できることにつながります。

裏地さん
私は何を見ても好き嫌いがハッキリしているので、基準がとても明快だと思います。

インタビュアー
ものを見る目は、経験の積み重ねなのか、生まれながらの資質なのか、どちらだと感じますか?

裏地さん
どちらもですね。ギフトはコミュニケーションツールなので、独りよがりではいけません。聴く力や話す力など、コミュ力は高めるべきです。
インタビュー取材の最中、ギフトに関して多岐にわたる話題となったものの、裏地さんは本当にいろんなことをご存知だと感じました。生け花では草月流の師範、茶道も嗜み、日本における伝統文化の素養が備わっているお方でした。
ギフトコンシェルジュを志す人に向けたメッセージ
仕事として成立させることはとても難しい。そう前置きをしながらも、ギフトをコンシェルジュすることは日本1億総人口みんなができることで、ハッピーな感じがして素敵だと話す裏地さん。人のためだけでなく、自分にギフトを贈ることの大切さを説いてくださいました。

裏地さん
自分が好きなものを選んでハッピーになり、人にお福分けをしていく。そういうところから始めていくといいかもしれないですね。
その上で、ギフトコンシェルジュとして自分が何ができるか深めていくことで、広がりが出ると感じているそうです。裏地さんとしては、お茶とお花を学ぶことで日本の四季やしきたりといった知識を実践的に培うことができたと話します。
ギフトを選ぶときは夏と冬ではセレクトの基準も大きく異なるもので、季節感が大切になります。また、ギフトを贈るときは基本的なマナーは身についておくと失礼がなく、ラッピングや作法も大事です。普段から様々なことに興味を持つとそれらのきっかけとして入りやすく、裏地さんにとってはお茶とお花だったのです。

裏地さん
ギフトコンシェルジュを志すなら、自分はギフトコンシェルジュですと言いきり、思いきって発信してみてくださいね。

インタビュアー
私自身としても励みになりました。この度は本当にありがとうございました。
ギフト選びのコツやおすすめの贈り物について
今回はギフトコンシェルジュの在り方を探るうえでとても貴重な機会になりました。ギフトコンシェルジュの第一人者である裏地桂子さんのインタビュー記事は二部構成でお届けします。裏地さんがギフトを選ぶために心掛けていることや実際に贈っているものをお聞きしましたので、第二弾もお楽しみください。